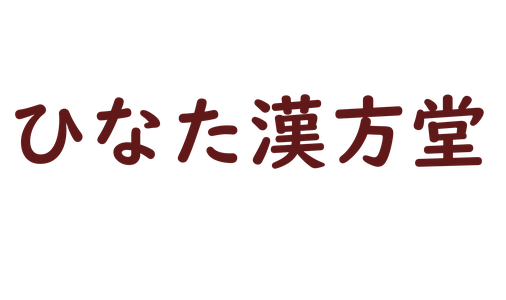不眠

「眠れない…」そんな夜は、心身ともに本当につらいものですよね。不眠と一言で言っても、その種類は様々です。寝つきが悪い入眠困難、夜中に何度も目が覚めてしまう中途覚醒、目覚ましよりずっと早く目が覚めてしまう早朝覚醒、そして睡眠時間は十分なのに朝起きても疲れが取れていない熟眠障害。それぞれに異なる辛さがあります。
私自身、普段はあまり不眠に悩むことはありませんが、何度かこの入眠困難を経験したことがあります。体が疲れているはずなのに、ベッドに入っても一向に眠気が訪れないのです。寝返りを打っても、時間が過ぎるばかりで、朝刊がポストに投函される音を聞いて「もうこんな時間か」と焦りを感じるほどでした。結局、ほとんど眠れずに朝を迎え、重い体で一日を過ごすことに。夜になればさすがに眠れるだろうと思いきや、また同じことの繰り返しで、夜になるのが憂鬱に感じるほどでした。幸い、私の場合は少しずつ元に戻っていきましたが、人によってはこの状態が長く続いてしまうこともあります。
中医学では、不眠は感情の変化と深く関係しているとされています。中医学には「怒・喜・思・憂・悲・恐・驚」の7つの感情があり、この中で不眠と特に関わりが深いのが「怒(怒る)」「思(思い悩む)」「憂(憂う)」「悲(悲しむ)」です。こうした情緒の変化が、体内の「心(しん)」「肝(かん)」「脾(ひ)」などの臓器に影響を与え、その機能が低下し気血が不足することで不眠につながるとされています。
皆さんもご経験があるかと思いますが、感情が高ぶったり乱れたりした際に眠れなくなることも多いのではないでしょうか。例えば、ストレスや不安で心がざわついて眠れなくなったり、悩みごとで頭がいっぱいになり寝付けなかったり。このように、情緒の乱れによる気血の不足や滞りなどが、中医学では不眠の大きな要因であると考えます。
もちろん、不眠の原因は感情の変化だけではありません。陰陽のバランスの失調や胃腸の不調など、さまざまな要因が複雑に絡み合って不眠を引き起こすこともあります。
すぐにでも試せる簡単な対策として、就寝前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのを控えましょう。スマートフォンを就寝前に使う場合には、ナイトモードなどを使用するとよいでしょう。また、夜間は明るい光を浴びることを避け、就寝時には寝室をできる限り真っ暗にすることがポイントです。
さらに、日中の過ごし方も大切です。適度な運動は質の良い睡眠につながりますが、就寝直前の激しい運動は避けましょう。また、規則正しい生活リズムを心がけ、毎日同じ時間に起床・就寝することで、体内時計が整いやすくなります。これらの小さな工夫が、眠りの質を高める第一歩となることも少なくありません。
当店では、お客様に合わせた漢方薬のご提案や、日々の過ごし方のアドバイスを通じて、穏やかな眠りを取り戻すお手伝いをさせていただきます。もし今、眠れないことでお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。